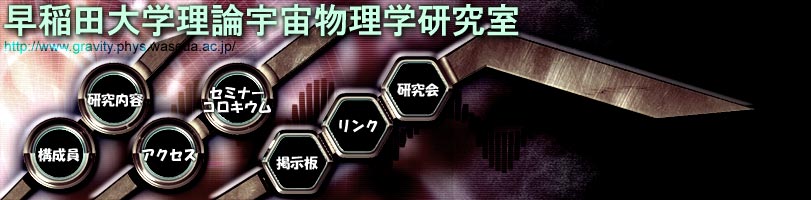
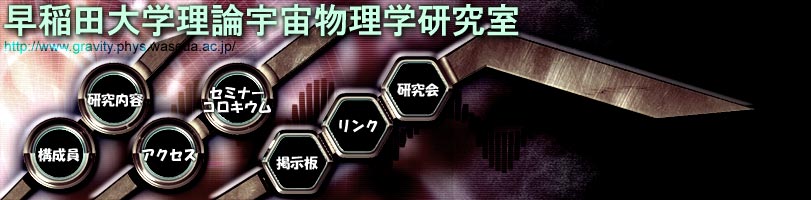 |
| Top Page→ 研究内容 |
| ■ 研究室紹介▼ プレプリントリスト▼ 内部情報▼ |
| 1. 構成 |
早稲田大学大学院先進理工学研究科・物理学及応用物理学専攻(早稲田大学先進理工学部物理学科) に所属し、
前田研究室、山田研究室のそれぞれで学生を受け入れている。
| 2. 研究 |
私たちの研究室は、宇宙・重力に関する現象に広く興味を持ち、研究を行っている。
論文速報、研究室の構成員によるコロキウム、外部の講演者によるセミナー等の会合を持ち、
研究室内外・国内外を問わず研究情報の交換および共同研究を積極的に行っている。
これら以外にも様々なテーマの少人数によるグループゼミが並行して行われており、
常に新しい研究テーマを模索している。また春と秋には学内で、
夏には合宿を行い各人の研究成果を発表している。
| 2.1. 宇宙論 |
近年の観測機器の進歩に伴い、超新星や宇宙背景輻射の観測などから宇宙の研究は飛躍的に進歩を遂げ、 ビッグバン宇宙論など宇宙に関しては多くのことが科学的に明らかにされてきた。 その一方で、現在の宇宙はダークエネルギーやダークマターといった起源が不明な物質が 9割以上もしめていることも明らかになった。これらはこれまでの常識的なアプローチでは解決されそうもなく、 基礎物理学における基本法則の根幹にも関わる重要な問題を提起している。 具体的には、主に以下の課題に取り組んでいる。
| 2.1.1. 初期宇宙 |
素粒子統一理論をもとにした新しい宇宙像(ブレイン宇宙)を研究しており、 この宇宙モデルでの宇宙の創生、インフレーション、再加熱、現在の加速膨張(ダークエネルギー)など へのさまざまな影響やその検証可能性などを調べている。これらの初期宇宙像は高次元宇宙モデルであり、 こういった高次元宇宙論の研究を通して、我々の宇宙はなぜ3次元か、なぜ反物質がほとんどない 物質優勢の宇宙が生まれたのか、ダークエネルギーが真空エネルギーだとするとなぜ不自然な小さな 値が選ばれたのか、といった時空や物質の起源に関わる根源的な問題に迫ることができるのではないかと考えている。
| 2.1.2. 大規模構造の起源と進化 |
通常、現在の銀河や銀河団などの宇宙の大規模構造は宇宙初期のインフレーションという 加速膨張期にできた量子揺らぎが古典化し、その密度ゆらぎが重力不安定性によって成長したと考えられているが、 これらの構造の種の生成メカニズムやそこから予言される物質分布の性質を調べ、 その観測的な検証可能性などを明らかにする。さらにその後の進化ではダークマターが必要不可欠であり、 これらの理論的起源やこれらを含めた自己重力多体系の統計的性質などを理論的および数値的な面から研究している。
| 2.1.3. ダークエネルギー |
現在の宇宙の加速膨張を引き起こしているダークエネルギーの研究も行っている。 これらは一様等方時空の仮定に基づくFriedmann方程式で解釈すると圧力が負の宇宙定数に似た 奇妙な物質の存在を示唆するが、原理的な困難を抱えている。この問題解決にはこれまでの基礎物理学を 根本から考え直す必要があるかもしれず、ダークエネルギーは現在のエーテルとなるかもしれない。 このような考えのもと、重力理論そのものの変更、素粒子理論統一理論からのアプローチ、 さらには非一様宇宙における見かけの効果の可能性などさまざまな可能性を考え、多面的に研究している。 上記1〜3の研究と並行してその観測的な検証可能性を調べることも重要な研究である。 特に宇宙の最古の情報を我々に伝えてくれる宇宙背景輻射のさらなる解析として偏向の情報や 広波長領域でのスペクトル観測などから宇宙の大規模磁場や初期の星形成期などの情報がわかるかもしれない。 また近年観測技術が進歩しているIa型超新星爆発、重力レンズ、バリオン振動などの観測や、 さらに将来期待される背景重力波やガンマ線バーストの観測によってもより最古の宇宙の姿が 明らかになる可能性があり、これらの研究が重要であると考えている。
| 2.2. 一般相対論・重力理論 |
一般相対性理論は重力を記述する理論として、宇宙論や天体物理学における基本法則となっている。 しかし、ミクロな世界では相対論は量子論と相性が悪く、量子重力理論は未だに完成されていない。 現在は、素粒子統一理論の立場から超弦理論(M理論)やその有効理論である超重力理論が、 また正準量子化の立場からループ重力理論がその有力な候補として研究されている。 そこで我々は、このような立場からも、その宇宙物理学への応用および基本物理学としての重力の研究に取り組んでいる。
| 2.2.1. 相対論的天体と重力波 |
ブラックホールは星の重力崩壊によって形成されると考えられており、
時空が極端にゆがめられた世界である。それでブラックホールは強重力場における物理学の最高の実験場といえる。
また、重力波は一般相対論から予想される時空のゆがみを伝搬する波である。
その透過性は極めて高く、観測されれば電磁波やニュートリノといった従来の観測手段を凌駕するであろう。
現在、日本をはじめとする世界各地のグループによってレーザー干渉計を用いた観測が始められており、
理論家のなすべき役割は、強重力場での天体現象から放出されるであろう重力波を理論的に予言することである。
これにより、重力波天文学が現実のものとなるとともに、強重力場における一般相対性理論を検証することができる。
また、超高密度における物理現象の解明にもつながるであろう。
重力波は「宇宙を見る第三の目」として新しい天文学を拓く時対されている。
我々は、一般相対性理論を基礎としてブラックホールや重力波に関連した強重力現象の研究を行っている。
具体的には次の課題について研究を進めている。
(i) カオス力学系におけるテスト粒子からの重力波
ブラックホールの回りのテスト粒子からの重力波を計算し、
その軌道のカオス性と放出重力波の相関を解析している。
(ii) ブラックホールと重力レンズ現象
重力レンズ現象を通して現実の相対論的天体(ブラックホールまたは裸の特異点)がどのように観測されるか、
それによってその天体の性質をどこまで特定できるか、について調べている。
(ii) 相対論的天体の形成
一般相対論的シミュレーション(数値相対論)を実行することで、
現実の相対論的天体がどのように形成されるか、どの程度の重力波を放出するか、
最終時空構造はどうなるかなどを研究する。この項目は目下、準備中である。
具体的な対象として非球対称な星の重力崩壊とブラックホール形成に着目し、
そのメカニズム及び重力波との相関の解明を行なう予定である。
さらに将来的には、現実的状態方程式、磁場、ニュートリノといった物理的素過程が
形成メカニズムに及ぼす影響を調べる予定である。この研究は山田研究室との共同研究である。
| 2.2.2.重力崩壊と時空特異点 |
一般相対性理論の基礎的問題に取り組んでいる。 漸近的平坦な定常時空を仮定するとブラックホールはKerr解の一意性が示され、 その解は安定性であることがわかっている。しかしながら、現実の星が重力崩壊することによって できる最終時空構造がブラックホール時空になるかどうかはまだわかっていない。 Penroseは「宇宙検閲官仮説」を唱え、裸の特異点は現実には現れないとしたが、 適当な条件の下では、重力崩壊において最終的に物理量が発散する裸の特異点が形成されることがわかっている。 この裸の特異点は外部と因果的につながっており、理論の予測可能性が失われてしまう。 この重力崩壊および最終時空構造問題は相対論の重要課題の一つである。 我々は、特異点形成付近での量子効果による放射の可能性や裸の特異点の安定性を探り、 重力崩壊の最終状態として裸の特異点が一般的であるかどうかを研究している。
| 2.2.3. 新しい重力理論と宇宙物理学 |
素粒子統一理論や量子重力理論を目指し、近年、新しい重力理論が注目されており、我々はそれらを用いた宇宙物理学の研究を行っている。
(i) 超弦理論とブレイン重力理論
近年では特に超弦理論に代表される素粒子統一理論において、高次元時空が注目を浴びている。
特に、ブレインワールドシナリオにおいては、TeV程度の比較的低いエネルギースケールで理論が統一され、
近い将来の加速器実験などで高次元ブラックホールが生成される可能性が指摘されている。
我々は、高次元ブラックホールを中心とした高次元重力理論の基礎研究を行っている。
また、超弦理論の有効理論である超重力理論を基礎に、ブラックホールやブラックリング、
ブラックブレインと呼ばれる様々なトポロジーを持つブラック“ホール”について研究を行っている。
具体的には、新たなブラックホール解の発見や安定性解析、動的な形成過程、熱力学的性質などの研究である。
(ii) ループ量子重力理論
4次元重力理論の正準量子化として現在最も有望なのがループ重力理論である。
ブラックホールは固有温度やエントロピーを持つことがわかっているが、
我々は、その統計力学的起源についてループ量子重力理論を用いたアプローチで研究をしている。
また、ループ量子重力理論の立場から宇宙初期特異点やブラックホール特異点回避の問題についても取り組んでいる。
最近の博士論文
最近の修士論文